2019/09/23 作成、2019/09/25 更新
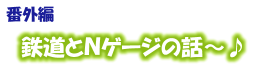

国鉄時刻表(1964年10月号)の復刻版

日本交通公社の国鉄時刻表(1964年10月号)の復刻版が発売されました。このページでは、当時の国鉄の時刻表や路線図から在りし日の風景を思い浮かべるために、近年に撮影した写真と共に掲載されている時刻表や路線図を少しだけ紹介します。
1. 超特急ひかり


1964年10月に開業した東海道新幹線は、「超特急ひかり」と呼ばれていました。復刻版の時刻表にも、こだまは「特急」、ひかりは「超特急」と記載されています。大宮の鉄道博物館には、当時の出発案内表示板が展示されており、ここにも「超特急ひかり 新大阪」と表示されています。ちなみに、鉄道博物館には、懐かしいパタパタ式の発車案内表示機(反転フラップ式案内表示機)も展示されています。
2. 天北線


1964年の北海道の路線図は、現在とは異なり、多くの路線が存在していました。そのひとつが、1989年 5月に廃止された北海道の天北線です。現在は、音威子府駅から幌延を通る西回りの宗谷本線だけが残っていますが、当時は浜頓別を通る東回りの天北線が存在しました。右の写真は、音威子府駅です。駅舎の資料室には、当時の写真などが飾られています。
3. 名寄本線、興浜線 興部駅


名寄本線の時刻表です。興部駅は、オホーツク海沿いに北上してきた名寄本線と興浜線の分岐点でした。1989年の廃線後は、駅舎跡に記念館と「道の駅おこっぺ」が建設されました。道の駅には、宿泊施設として使用されているキハ22「ルゴーサ・エクスプレス」の車両が保存されています。
4. 大畑線と大湊駅


青森県の下北半島には、2001年まで大畑線が走っていました。大畑線は、大湊線の終点である大湊駅の1つ手前の下北駅からオホーツク海側に出て北上して大間の手前にある大畑まで20km弱の短い路線でした。大畑線が廃線となった現在では、大湊駅が本州の北の終着駅となっています。左の写真は、現在の大湊駅です。津軽半島側の終着駅は、1964年当時も現在も三厩駅で変わっていません。
5. 国鉄の運賃(1964年10月)


国鉄時刻表には、運賃表も掲載されています。1964年10月時点では、初乗りが10円でした。鉄道博物館には、初乗りが100円の普及型の自動券売機の隣に、古い20円区間用のオレンジ色の自動券売機が展示されています。おそらくこの古い自動券売機が使用されていた時代の運賃ですね。
6. 函館本線 神居古潭駅


函館本線の神居古潭駅が残っていた頃の時刻表です。神居古潭駅は、1969年10月の電化に伴う路線変更により、廃駅となりました。現在、神居古潭駅の跡地には、プラットフォームと駅舎の一部が保存されており、構内にはD51-6号機、C57-201号機、9600系29638号機の 3車両が展示されています。
7. 北海道 広尾線(愛国駅~幸福駅)


1987年 2月に廃止された北海道 広尾線の時刻表です。当時、愛国駅から幸福駅行きの切符が話題になりましたが、廃線となった現在もこの2つの駅は、保存されています。幸福駅の構内には、キハ22が展示されていました。ちなみに、愛国駅には 9600系の蒸気機関車19671号機 が展示されています。
8. 急行オホーツク

9. 特殊弁当(時刻表の欄外)


昔の時刻表は、欄外にその地方の名物である「特殊弁当」の紹介が記載してありました。駅弁を販売している駅は、時刻表の駅名の隣には、「弁」の印があります。上越線・信越本線のページを見ると水上駅に「釜めし150円」と書かれていました。昔から峠の釜めしは、定番の駅弁ですね。左の写真は、九州の肥薩線の人吉駅のホームで駅弁を販売している駅弁売りさんです。
10. 青函連絡船(青森駅、八甲田山丸)


昭和の国鉄で忘れてはいけないのが、連絡線。中でも青函連絡船は、有名な航路です。1964年の時刻表には、東北本線のページに函館~青森間の青函連絡船発着時刻が記載されています。1988年 9月(昭和63年)の航路廃止に伴い、青森桟橋側には八甲田丸が、函館桟橋側には摩周丸が展示されています。八甲田山丸は、列車を収納している車両甲板も見学することができます。
11. さくら・みずほ・あさかぜ・はやぶさ・富士


「1レさくら」、「3レみずほ」、「5レあさかぜ」、「7レはやぶさ」、「9レ富士」、古き良きブルートレインの時刻表です。ちなみに、上の写真は東京駅に入線する「8レはやぶさ」です。左の写真は、この時刻表が発売された1964年10月のダイヤ改正により、運行区間が東京駅~浜田駅間に変更されたブルートレイン出雲です(1986年撮影)。
12. 東京駅 8~15番ホームの変遷


1964年10月の国鉄の時刻表を見ると、東京駅に入線する東海道線が 8番ホームから15番ホームに割り当てられています(正確には、11番線が機回し用、13番線が横須賀線)。東海道新幹線開業直後の東京駅は、16番線が無く、17~19番線が新幹線用のプラットホームでした。
上と左は、1986年に撮影した写真ですが、1975年の山陽新幹線開業に伴い新幹線の発着本数が増加したため、14番線以降を新幹線用に、在来線は12番線まで、と変更されました。この当時、10番線と12番線の間にある回送線路を使用してブルートレインの機回し(牽引車両の付け替え作業)が行われていました。
13. 展望車


昭和39年の国鉄時刻表には、列車名欄に「展」の文字が記載されていました。特急「つばめ」、「はと」でもお馴染みの展望車のマークです。鉄道博物館には、元々青梅鉄道公園に展示されていたマイテ39 11が移設展示されており、現在でもその姿を見ることができます。現役の列車では、やまぐち号が牽引するオハフ13 701などが存在します。
14. 急行「あけぼの」


北斗星と共に最後まで頑張っていたブルートレイン「あけぼの」も時代と共に移り変わっていった列車でした。1964年当時は、青森発、仙台行きの急行「あけぼの(702レ)」でした。時刻表を見ると金沢行きの「しらゆき(504レ)」を連結した混成編成で秋田駅で分離していたことが判ります。あけぼのは、1970年にお馴染みの寝台特急(ブルートレイン)に格上げされて、2014年まで運行されました。
15. 瀬戸、宇高連絡線


1964年の瀬戸は、東京駅~宇野駅を結ぶ急行列車でした。1972年に瀬戸は、特急列車に格上げされます。当時は、本州と四国を結ぶ橋が無いため、時刻表には宇野駅と高松駅を結ぶ宇高連絡線が記載されていました。終点が岡山県の宇野駅から四国の高松駅に延長されたのは、瀬戸大橋が開業した1988年 4月です。その後、1998年に現在の寝台特急電車「サンライズ瀬戸」が誕生しました。長い歴史を感じます。
16. 信越本線 碓氷峠越え(横川駅~軽井沢駅)


言わずと知れた、信越本線の横川~軽井沢駅間、碓氷峠越えの時刻表です。ここは、あまりにも有名なので説明不要でしょう。現在も眼鏡橋こと「碓氷第3橋梁」は、観光名所として保存されています。長野新幹線の開業に伴い、横川駅が高崎側の終着駅となった信越本線ですが、JR東日本が毎年D51-498号機やC61-20号機を利用した臨時列車を運行しています。
17. 準急かいじ、特急あずさ


東京近郊ではお馴染みの特急「あずさ」ですが、昭和39年には存在しませんでした。当時の中央本線の国鉄時刻表には、準急「かいじ」の時刻が掲載されています。「かいじ」は、後に加わった「あずさ」と共に現在も中央本線の特急として活躍しています。「準急」どころか「急行」ですら廃れてしまった現在のJRとは異なり、昭和の国鉄時刻表は見応えがあります。
18. 特急列車の編成


国鉄時刻表には、代表的な特急や急行列車の編成表が掲載されています。1964年(昭和39年)は、ブルートレインブームが来る直前ですが、寝台列車の全盛期です。さくら、みずほ、あさかぜ、はやぶさ、富士等、名だたるブルートレインは、客車14両+電源車+牽引車の計16両編成でした。函館駅や長万部駅など、かつてブルートレインが停車した駅は、今でも長いプラットフォームが残っています。
19. 下河原線(中央本線支線)


1973年 4月に廃止された下河原線の時刻表です。下河原線は、中央本線の支線で国分寺駅から、北府中駅、東京競馬場駅のわずか2駅のみの路線でした。下河原線には貨物線があり、北府中駅の先で分岐した貨物線は、現在の府中市内を走っていました。廃線後の貨物線の跡地は、下河原緑道として整備されており、現在もレールの一部が残っています。下河原線は、武蔵野線の開通に伴い、廃止されました。
20. 国鉄中央本線 東小金井駅開業


1964年10月の時刻表の巻頭には、中央本線の東小金井駅の開業案内が掲載されていました。東小金井駅は、武蔵境駅と武蔵小金井駅の間に新設されました。中央本線は、2010年の高架化事業により、地上に存在した旧駅舎は全て撤去されて、高架駅になりました。左の写真は、撤去作業中の武蔵小金井駅の地上プラットフォームです。
21. 青梅線 氷川駅(奥多摩駅)


時代と共に変わっていった駅名はたくさんあります。ここ青梅線の終点「奥多摩駅」も 1971年までの駅名は、「氷川駅」でした。現在の奥多摩駅は、週末になると多くの登山客で賑わっています。奥多摩駅の周辺では、当時存在した水根貨物線の廃線跡を見ることもできます。
22. 帝都高速度交通営団(地下鉄線)


国鉄の時刻表には、私鉄や地下鉄の時刻表も一部掲載されています。昭和39年の時刻表には、「帝都高速度交通営団」の時刻が記載されていました。帝都高速度交通営団は、2004年に現在の東京メトロに代わりました。この時代は、初乗り運賃が20円だったことが判ります。
国鉄時刻表(1964年10月号、復刻版)は、Amazon で販売しています。価格は、1,620円 1,650円(税込)です。全568ページの時刻表は、見応え抜群! 復刻版とは言え、新品で購入できる国鉄時代の時刻表は、お勧めの一品です。

